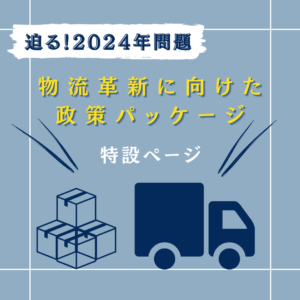物流におけるBCP対策とは、多様な災害に対して、倉庫業・トラック業等の物流企業と荷主企業がサプライチェーンを維持するために連携して事業の継続に取り組むための体制構築をすることを指します。
今回は、物流のリスク管理に欠かせないBCP対策の策定ポイントを詳しく解説します。緊急時に物流がストップするリスクを回避するための重要な課題となりますので、ぜひ参考にしてください。
SCM/3PL/物流のお悩みを解決したい方へ

プロレド・パートナーズでは、現状把握から施策の立案・実行まで一貫したサポートが可能となります。SCM改善について皆様からのご相談をお待ちしております。
物流のBCP対策とは?
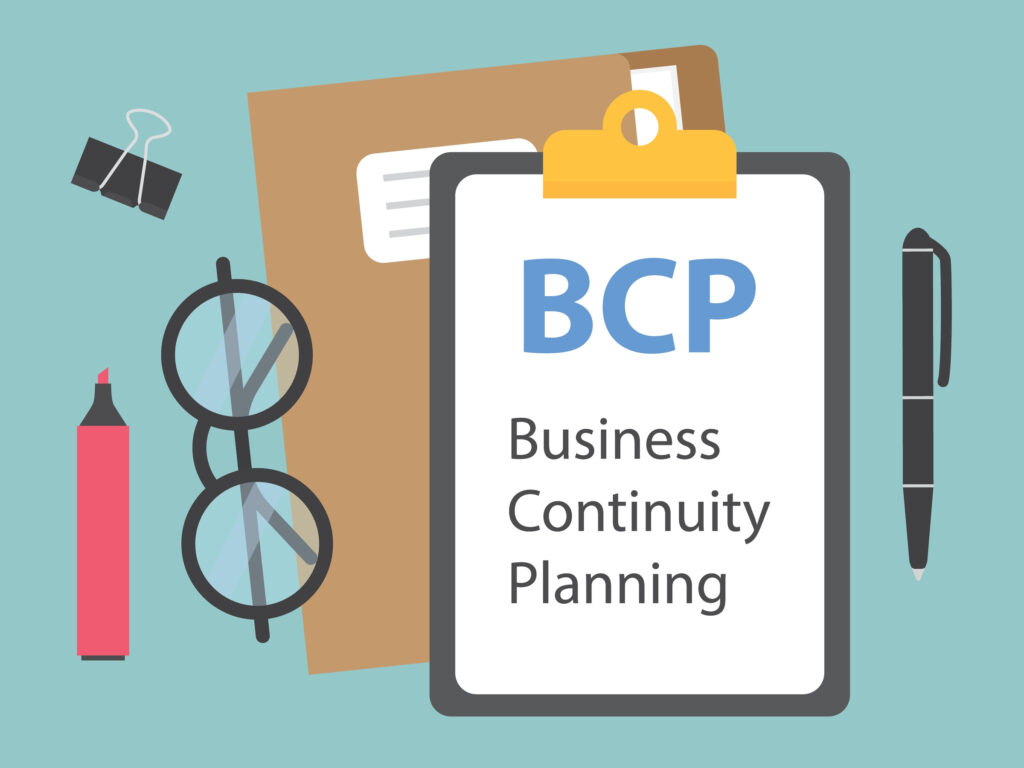
BCP(Business Continuity Plan)とは、災害などの危機的状況から早期に事業を復旧し、重要業務を滞りなく続ける手段を取り決めておく「事業継続計画」のことです。
物流におけるBCP対策とは、多様な災害に対して、倉庫業・トラック業等の物流企業と荷主企業がサプライチェーンを維持するために連携して事業の継続に取り組むことを指します。
BCP対策を実行に移すには相応のコストや工数がかかりますが、災害時に物流が止まる要因を最低限に抑えることができ、早期復旧が可能になります。
物流のBCP対策の重要性

日本では近年、地震・津波・大雪などの自然災害が頻発しており、いつどこで被災してもおかしくない状況です。自然災害をはじめ、感染症といった不測の事態に対応するには、平時からBCP対策を進めることが重要です。
2011年3月に起きた東日本大震災では、多くの物流企業が対応に追われ、事業の継続に支障が生じました。これを受けて国土交通省では、2015年3月に「荷主と物流事業者が連携したBCP策定のためのガイドライン」を策定し、荷主や物流事業者のサプライチェーン維持に係る対策を講じています。
地震や津波と異なり、台風・大雨・大雪等の風水害は、ある程度予見できるものです。そのため、事前に適切な対応を取ることで、災害の影響を軽減または回避できる可能性があります。
BCP対策を怠ると、事業再開までに膨大な時間と費用を費やしてしまい、最悪の場合は事業が再起不能になることもあります。企業の円滑な経営を維持するには、BCP対策が欠かせません。
従来の物流BCPは、いつ来るかわからない不足の事態に備えるものでしたが、今後はいつ何が起きてもおかしくないという考えのもとで物流BCPを策定する必要があります。
緊急時のリスク対応を行うことにより、被害を受けたときの廃業の危険性を軽減でき、自社の競争優位性の向上につながります。
物流BCP対策の策定ポイント
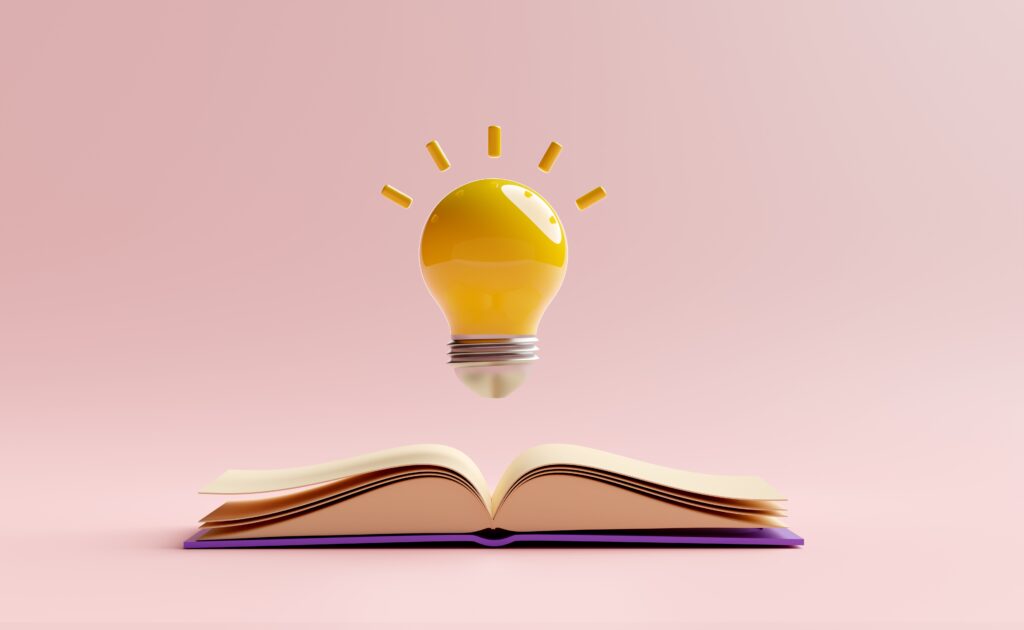
BCP対策が重要であることはわかっていても、具体的にどのような内容を作成すればいいのかわからず、対策が後回しになっている企業も多いのではないでしょうか。
ここでは、国土交通省が作成した「荷主と物流事業者が連携したBCP策定のためのガイドライン」を基に、物流BCP対策の策定ポイント4つを説明します。
- 防災対策
- 発災直後の措置
- 復旧対策の実行
- 実効性強化
1.防災対策(事前の体制準備)
災害が起こった時のサブライチェーンを維持するために、防災対策を立案します。
| 項目 | 内容 |
| 人材の確保・育成 | BCP担当者の確保、教育体制の整備 |
| BCP発動時の体制の確立と人的応援・支援体制の整備 | BCP発動時の組織体制の確立、企業間の人的な応援・支援体制の整備、復旧に必要な備品等の確保 |
| 施設・輸送力の確保対策(BCPを考慮したネットワークの構築) | サプライチェーン維持のための施設・輸送力の確保、代替輸送・施設・作業のスキーム構築、施設管理者との連携計画、在庫と燃料の備蓄 |
| 作業の標準化・従業員の多能化 | 異なる物流施設同士の作業を標準化、平常時からの教育による従業員の多能化 |
| 行動マニュアルの作成と想定される被害への対応に関する協議等 | 行動マニュアルの作成と優先的事項の設定、定期的な見直し、事前の被害想定 |
| 発災時の被害情報等の共有 | 交通インフラの被災状況や復旧状況に関する情報を収集・共有する方法の決定 |
| ITシステムの活用及び標準化 | 貨物情報のITシステム化、クラウドシステムを活用したデータのバックアップ |
災害時にサプライチェーンを維持するには、荷主と物流事業者が連携したBCPが必要です。そのためには、サプライチェーン全体を把握している人をBCP担当者にし、緊急時の体制を構築する必要があります。
平常時よりハザードマップを確認して、代替手段や代替輸送ルートの提案しやすい話し合いの場等を設けましょう。必要な情報を共有して、信頼関係を構築することが大切です。
2.発災直後の措置
災害が発生した後の対応について、計画を立てます。
| 項目 | 内容 |
| 従業員等の人的被害状況の把握 | 従業員とその家族の安否を確認 |
| 荷主と物流事業者の連絡(連絡機能の確保) | 非常用通信設備の活用して、荷主と物流事業者の相互の被害状況等の確認 |
発災時は物流継続のために従業員が一丸となって対策を進めていく必要があることから、人的被害状況の把握が最優先事項となります。
安否確認を行う手段として、以下の方法が有効です。
- 災害伝言ダイヤル
- LINE
- Twitterなどのアプリ
また、荷主と物流事業者においては、非常用通信設備等の多重な通信手段(衛星電話、MCA無線等)を活用して、速やかに相互確認を行いましょう。
事前に担当者・通信手段・確認事項をリスト化しておくと、万が一のときに速やかな対応が可能です。
3.復旧対策の実行
災害時のダメージを抑えてサプライチェーンを復旧するためには、以下の取り組みが必要です。
| 項目 | 内容 |
| 行動計画に基づく対策の実行 | 目標復旧時間や最優先商品、重点業務等を柔軟に決定し、災害対策を実行 |
| 燃料の確保 | 発災時に燃料の備蓄量や調達可能量を常時把握、燃料の共有や確保情報の共有 |
荷主と物流事業者は、災害規模や自社の状況に応じて優先する重点業務等を決定し、災害対策を実行することが重要です。
特に物流事業者は、発災時に国や自治体等からの支援物資輸送の要請が発生するため、どの範囲までどのような順序で対応するかを、トラックの過積載運転等による2次被害の防止も考慮した上で、 計画的に行うことが大事です。
復旧時の燃料確保も重要なポイントです。東日本大震災では、燃料の確保ができないことが原因で業務が滞るケースが多発しました。そのため、物流の復旧において燃料の確保は極めて重要です。
4.実効性強化
万が一の時に素早く行動できるように、平時から準備できることを計画します。その時のために、下記の内容を決めておきましょう。
| 項目 | 内容 |
| リスクマネジメント | 高速道路の不通やオフィスの倒壊など、想定外の事態をシミュレーションする |
| 定期的な訓練や反復実施を継続 | 緊急連絡網、バックアップデータの稼働訓練、対策本部の立ち上げ等、具体的な訓練を行う |
| BCPの継続的な見直し | 国や自治体の対策が変わるごとに、BCPをバージョンアップしていく |
地域で起きた災害や復旧の方法について、国や自治体の対策が変わることもあります。BCP対策の計画を立てたら終わりではなく、災害対策の最新情報に合わせて計画を常にバージョンアップしていきましょう。
物流BCPで不可欠な荷主・物流事業者の連携

物流BCPに取り組むときは、物流事業者だけでなく、荷主と互いに連携した対策が欠かせません。
実際に荷主・物流事業者間で協議体制を構築している割合は7割(荷主71.4%、物流事業者67.6%)であり、物流事業者・着荷主間では 34.4%、元請物流事業者・下請物流事業者間では 41.8%にとどまっています。(参考:多様な災害に対応したBCP策定ガイドライン ~荷主・物流事業者の連携による安全で強靭な物流の実現に向けて~|国土交通省)
この現状を打破するには、物流BCP対策に関する会議の場を設けたり、災害時の目標復旧時間や優先商品などの情報を事業者と荷主間で共有したりするなど、普段から信頼関係を構築することが重要です。
平常時よりハザードマップを確認し、代替輸送の連携体制を整備するなど、代替輸送ルートの決定方法を荷主・物流事業者間で事前に取り決めておきましょう。
国土交通省のホームページにある「災害・防災情報」では、道路の復旧状況や空港・航空・鉄道各社の運行状況、地震・津波情報等が集約されているため、情報収集や代替輸送ルートを選定する際に役立ちます。
まとめ
物流BCP対策とは、災害や事故などの緊急時に物流を止めずに継続するための計画を指します。物流BCPは商品供給の命綱であり、早期の策定が必要です。
BCP構築にはコストがかかり、予算が無い状態で短期的に実施することは困難です。BCPの検討自体も段階的に予算化し確実に進めていきましょう。
プロレド・パートナーズでは、物流BCP対策についてコンサルティングを承っております。BCPの策定にかかるコストや労力などの負担を軽減し、本業に専念できる体制づくりをサポートいたします。
計画立案からサプライヤーとの協議まで、 コスト削減に関わる業務の一括対応が可能です。物流BCP対策を検討している担当者の方は、ぜひプロレド・パートナーズへお気軽にご相談ください。
SCM/3PL/物流のお悩みを解決したい方へ

プロレド・パートナーズでは、現状把握から施策の立案・実行まで一貫したサポートが可能となります。SCM改善について皆様からのご相談をお待ちしております。